コラム
警備員に多いクレームの原因と防止策|改善ポイントと対応フローを解説
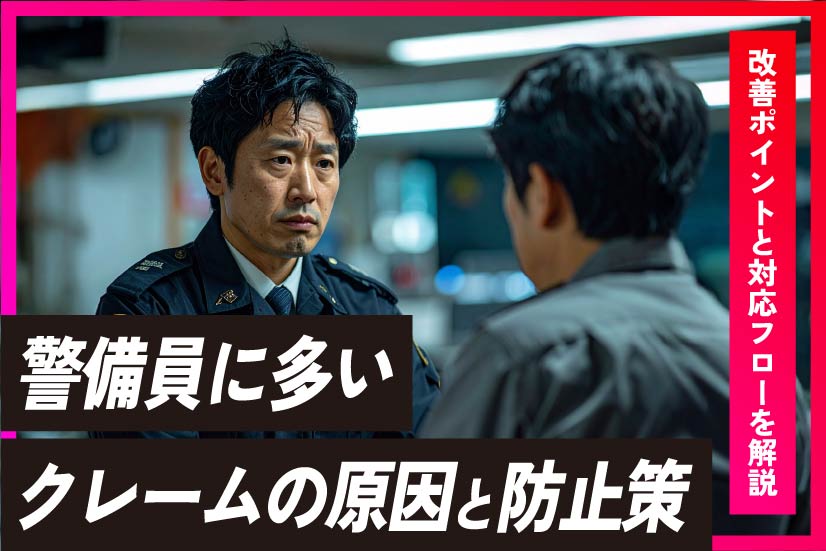
警備員へのクレームは、あらゆる現場で日常的に発生しています。態度や言葉遣い、指示の仕方といった小さな行動が原因となり、施設全体の評価に影響することもあるのです。
本記事では、警備員に多いクレームの原因と防止策、発生しやすい場面ごとの注意点、基本的な対応フローを詳しく解説します。また、正当なクレームとカスタマーハラスメントの違いも紹介しますので、参考にしてください。
目次
警備員に寄せられる典型的なクレーム例と防止策

警備員へのクレームは、接客態度や対応の些細なやり取りから発生します。特に多いのは次の4つです。
- 横柄・威圧的な態度
- 丁寧さを欠いた言葉遣い
- 高圧的な指示や案内
- 勤務中の態度や姿勢への指摘
それぞれの原因と防止策を説明します。
横柄・威圧的な態度
警備員は規則順守のため毅然と対応する必要がありますが、声の大きさや語尾、視線によっては圧迫感を与えかねません。例えば「睨まれたように感じる」「腕組みで立たれると怖い」といった内容がクレームにつながることもあります。
防止策として表情を和らげ、両手を軽く前に揃えるなど、威圧感を与えない姿勢を心がけましょう。
丁寧さを欠いた言葉遣い
警備員がタメ口や乱暴な言葉遣いをすると、利用者は不快感を覚え、軽んじられていると感じます。例えば「注意の仕方がぶっきらぼうで嫌な気分になった」といった声がクレームにつながることもあります。
防止策としては、来館者や通行人など立場の異なる相手に合わせ、丁寧な敬語を用いながら、状況に応じた配慮ある話し方を心がけることが大切です。
高圧的な指示や案内
命令口調の指示や案内は、利用者に圧迫感や不快感を与え、反発やクレームにつながる恐れがあります。例えば「早く動いてください」「そこは通らないで」といった言い方が該当します。
混雑時や緊急時には迅速な対応が必要ですが、落ち着いた身振りと状況を伝える一言を添えることで、誤解や摩擦を防げます。
勤務中の態度や姿勢への指摘
警備員の居眠りや私語、持ち場を離れる行為は、「真面目に勤務していない」と受け取られ、クレームの原因になります。例えば「立ったままスマホを操作していた」「持ち場を長時間離れていた」といった指摘です。
警備員の振る舞いは現場全体の信頼感に直結するため、姿勢や所作を含め、常に誠実な対応を心がけましょう。
クレームが発生しやすい場面と注意するべきポイント

クレームには、現場の種類や状況によって起こりやすいパターンがあります。ここでは、場面ごとの特徴と注意点を説明します。主な場面は、以下の通りです。
- 商業施設での警備
- 駐車場の警備
- 建設・工事現場の警備
それぞれの特徴と注意点を解説します。
商業施設での警備|来館者への丁寧な対応を徹底
商業施設での警備では、来館者と接する瞬間の心配りが信頼を生み、クレームを未然に防ぎます。
例えば道を尋ねられたときに、「分かりません」と伝えるだけでは冷たい印象を与えますが、「申し訳ありません、正確には分かりませんが、インフォメーションはあちらです」と補足すれば印象は大きく変わるでしょう。
巡回中の声掛けも柔らかい口調と落ち着いた所作を意識すれば、不快感を与えず目的を果たせます。
駐車場の警備|車両誘導の分かりやすさとマナーを意識
駐車場の警備では、分かりやすい誘導と礼節ある対応がクレームを防止します。例えば手信号や誘導灯のタイミングが悪ければ混乱を招き、「誘導が下手」と苦情になることもあるでしょう。
また、強い口調や急かす仕草は、ドライバーの苛立ちを生みます。運転中は余裕がない人も多いため、焦らせず安心感を与える応対を意識しましょう。
関連記事:警備員必見!誘導灯(誘導棒)の振り方と効果的な使い方を解説
関連記事:車両のバック誘導合図の基本と種類|プロが教える実践テクニックを解説
建設現場・工事現場の警備|安全確保と近隣への配慮
建設・工事現場の警備では、安全確保と近隣への配慮が信頼や現場運営の円滑さに直結します。警備員は通行人や住民と接する場面が多く、対応次第で印象が変わります。
例えば道路工事で歩行者や車を止める際、説明がなければ「何も言われず待たされた」と不満を招くこともあります。日頃から挨拶や説明を丁寧に行い、危険時は理由を添えて協力を求めましょう。
関連記事:建設現場における道路工事の安全対策手法9選!事故発生要因と想定リスクも紹介
警備員クレームへの基本的な対応フロー

警備員がクレームを受けた際は、慌てず手順に従うことが大切です。対応の流れは以下の通りです。
- 相手の意見を尊重した傾聴の姿勢
- 誠意を前提とした冷静な対応
- クレーム内容と原因の正確な把握
- 適切な解決策の提案と実行
- 記録・報告と再発防止策の徹底
それぞれについて詳しく解説します。
相手の意見を尊重した傾聴の姿勢
まず、相手の話を遮らずに最後まで聞くことが基本です。相手が不満を話す目的は、解決だけでなく、聞いてほしいという思いがある場合も多く、真摯に聞くだけで感情が和らぐことがあります。
傾聴により、苦情の原因がどこにあるのか(利用者側・警備側・施設の運用上など)も明確になりやすくなります。
誠意を前提とした冷静な対応
感情的な応対は避け、常に落ち着いた姿勢を保ちましょう。相手が感情的でも、警備員は冷静で丁寧な言葉づかいを心がけ「ご意見ありがとうございます」「ご不便をおかけし申し訳ありません」など誠実な対応で信頼を保ちます。
警備側に非がある場合は、謝罪の意思を明確に示しましょう。相手が落ち着かないときは「責任者に確認のうえ、適切に対応いたします」と伝え、必要に応じて引き継ぎます。
クレーム内容と原因の正確な把握
相手の不満の具体的な内容や、問題が発生した状況・原因を整理しながら丁寧に確認します。「いつ・どこで・どのような経緯で起きたのか」といった基本情報を伺い、正確な事実関係の把握に努めましょう。
ただし、相手の話のみで早急に判断せず、必要に応じて第三者の証言や監視カメラ映像など、客観的な情報による裏付けも行ってください。
適切な解決策の提案と実行
原因が特定できたら、可能な範囲で解決策を提示し実行します。例えば「ただちに誘導方法を見直します」「関係者に申し伝えます」といった具体的な対応は、相手に安心感を与えるでしょう。
その場での対応が難しい場合は、「5日以内に担当部署よりご連絡します」など、今後の流れを明確に伝えましょう。
記録・報告と再発防止策の徹底
対応後は、クレームの内容や経緯を社内で記録・共有します。警備業法では警備会社に苦情処理簿の作成・保管義務があります。
現場担当者は速やかに上司や会社へ報告し、原因を整理して再発防止策を実行しましょう。クレームを単なる苦情で終わらせず、業務改善とサービス向上につなげることが重要です。
正当なクレームとカスタマーハラスメントの線引き

現場でのクレームには、業務改善につながる正当なものと、理不尽なカスタマーハラスメント(カスハラ)があります。
正当なクレームは、警備員の不備やミスで利用者に不利益や不快感を与えた場合の指摘です。カスハラは過剰な要求や執拗な非難など、個人を追い詰める言動を指します。
正当なクレームには真摯に対応し改善を図るべきですが、カスハラには警備員一人で対処せず、速やかに上司や警備会社へ引き継いでください。不当な要求には毅然と対応し、必要に応じて警察や法的措置も検討しましょう。
まとめ
クレームへの適切な対処は、サービス向上のヒントを得るチャンスにもなります。苦情を分析すれば警備体制の弱点が見え、対策により現場の信頼度を高められます。
現在の警備会社に不安があれば、信頼できる会社への見直しも検討しましょう。警備会社紹介サイト「警備ドットコム」なら、全国の警備会社をまとめて比較でき、業務内容や勤務形態に合わせた見積もりも確認できます。最短即日対応も可能なので、ぜひ活用してみてください。

